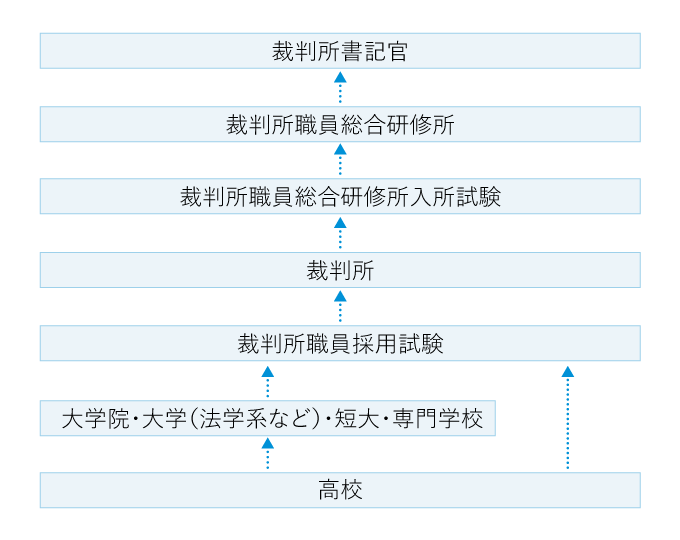裁判所書記官とは?
裁判所書記官の身分は国家公務員です。
法律の専門家であり、法廷立会,調書の作成,証明書の発付,執行文の付与のほか,支払督促の発付等を行います。
紛争を抱えて裁判所に訪れた人に対して手続の流れや申立ての方法を懇切に説明したり,適切な紛争解決に結びつける手続案内等も行っています。
民事、刑事、家事、少年といった裁判手続のあらゆる場面において,高度な法的知識に基づき様々な事務を担当し,適正迅速な裁判の実現を果たさなければならない仕事です。
裁判所書記官の仕事内容
裁判所書記官は次の裁判所に配置され、手続法の専門職として裁判事務に行います。
- 最高裁判所(大法廷・小法廷)
- 高等裁判所事件部(民事・刑事)
- 地方裁判所事件部(民事・刑事)
- 家庭裁判所事件部(家事・少年)
- 簡易裁判所事件部・係(民事・刑事)
次に仕事内容は以下のようなものがあります。
- 窓口案内・受付
- 裁判の審理計画・スケジュール管理
- 裁判立会(調書作成)
- 訴訟関係人との連絡調整、手続説明
- 事件記録の保存
- 執行文付与
- 支払督促
裁判所書記官の固有権限の仕事もありますが、民事裁判や刑事裁判では裁判官の訴訟指揮に従って、協働して裁判運営を行っています。
裁判員裁判など著名事件の裁判に立ち会うこともあります。

裁判所書記官であっても、後で述べますが、事務局部門(総務課・人事課・会計課など)の係長、課長補佐、課長として裁判所書記官の資格を持ちながら裁判所事務官として一般事務に就くこともあります。
裁判所書記官になるには?学歴は必要?
裁判所書記官になるためには、まず裁判所事務官の採用試験に合格する必要があります。
裁判所事務官として経験を積み、年に一度の裁判所職員総合研修所入所試験に合格しなければなりません。
法学部卒は1年間(一部生)、それ以外は1年6カ月間(二部生)の研修を終えると、裁判所書記官の辞令を受けて全国の裁判所に配置されます。
裁判所書記官になるためには、必ず法学部卒である必要はありません。
法学部以外の学部卒、専門学校、高校卒業など学歴は問われず、裁判所事務官であれば誰でも裁判所書記官の道が開かれています。
分かりやすいチャートがありましたので参考に掲載します。